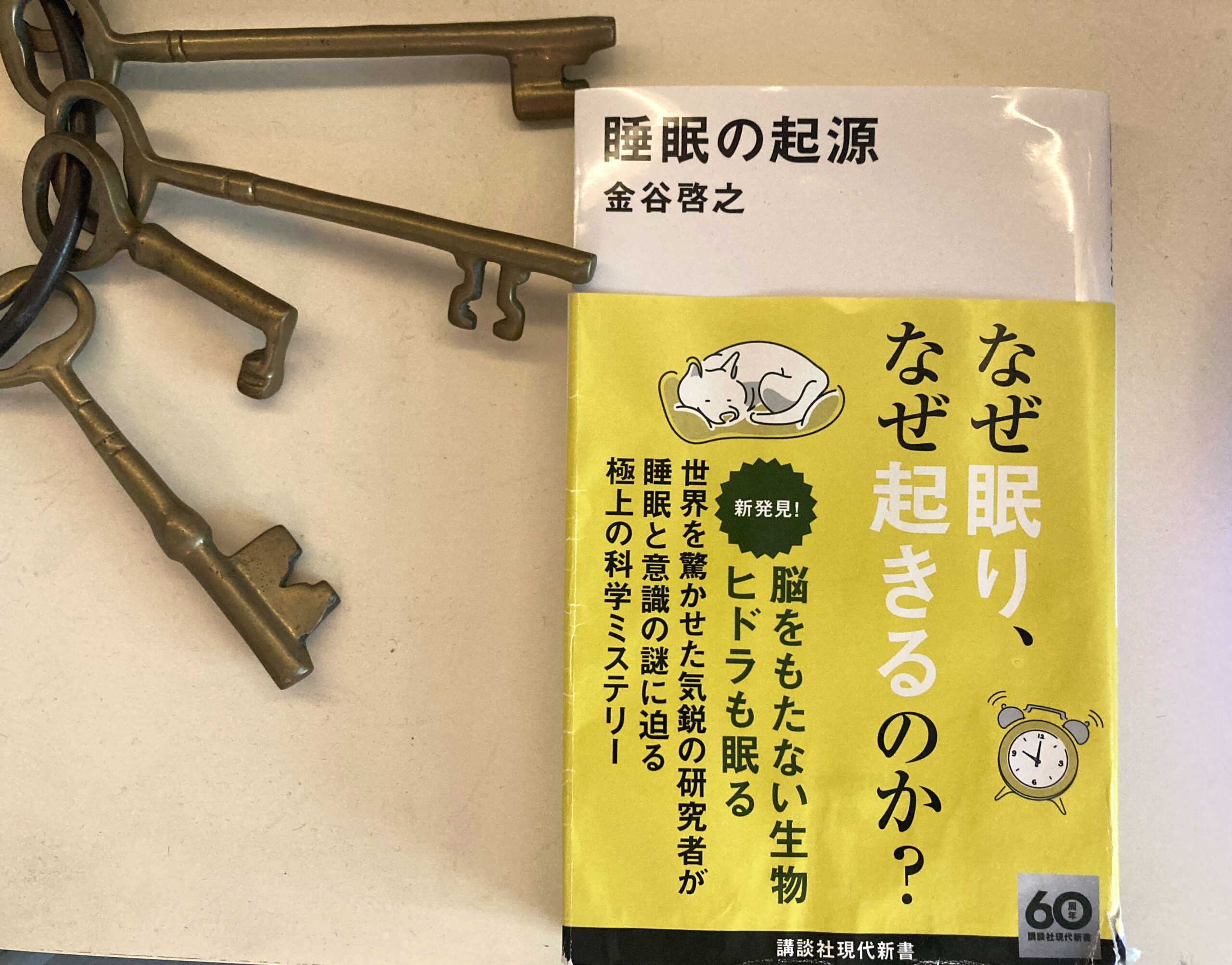「睡眠の起源」を読んで
私たちは普段、「眠りとは、
「疲れたから眠る」「エネルギーを補うために眠る」。
それはごく自然で、誰もが納得する“眠りの役割”として、
けれど、
それが、近年注目を集めている『睡眠の起源』という一冊です。
それが、近年注目を集めている『睡眠の起源』という一冊です。
この本では、「実は“眠っている状態”こそが、
つまり、「活動が例外であり、
つまり、「活動が例外であり、
著者が研究対象とするのは、なんと脳を持たない小さな生物──
このヒドラは、神経系を持たずとも、周期的に動きを止め、
“眠りのような状態”を繰り返しているのだそうです。
このヒドラは、神経系を持たずとも、周期的に動きを止め、
“眠りのような状態”を繰り返しているのだそうです。
驚くべきは、「眠るために脳はいらない」ということです。
私たちは、
私たちは、
このことは、私たちの暮らし方や、
「効率的な睡眠」や「生産性のための睡眠」といった“
「効率的な睡眠」や「生産性のための睡眠」といった“
そうすると、「眠ること」は私たちが“本来の自分に戻る”
そしてその“戻る過程”を支えるのが、心身をやわらかく整える「
そしてその“戻る過程”を支えるのが、心身をやわらかく整える「
たとえば、波の音や風の音、鳥の声。
あるいは音楽でも、人の鼓動のリズムに近い1/
こうした音は、脳を刺激するのではなく、「感覚を静かにほどく」
あるいは音楽でも、人の鼓動のリズムに近い1/
こうした音は、脳を刺激するのではなく、「感覚を静かにほどく」
音に包まれながら眠るという行為は、もしかすると、
私たちは、睡眠を単なる休息や回復ではなく、「感覚を解放し、本来の自己とつながる時間」ととらえています。
『睡眠の起源』という視点は、その考え方をより深く、
脳がなくても眠る。
それは、「眠り」が知性や思考を超えたところにある、“
それは、「眠り」が知性や思考を超えたところにある、“